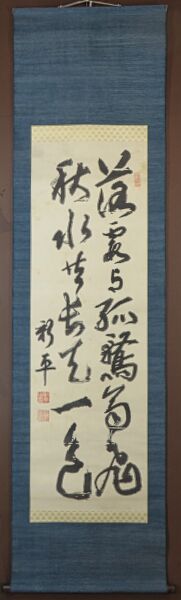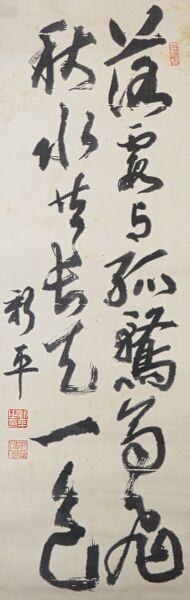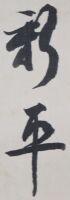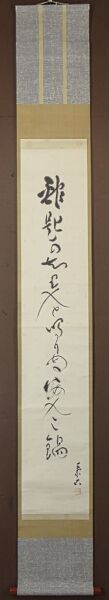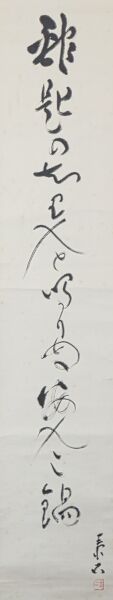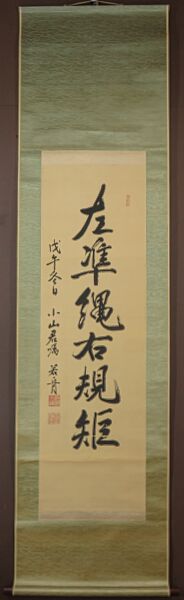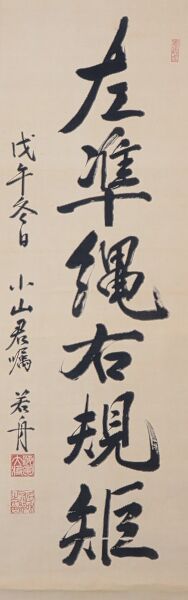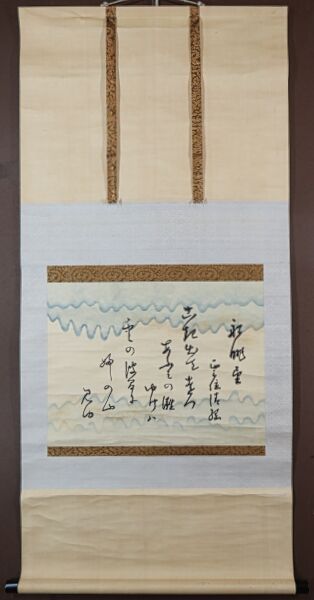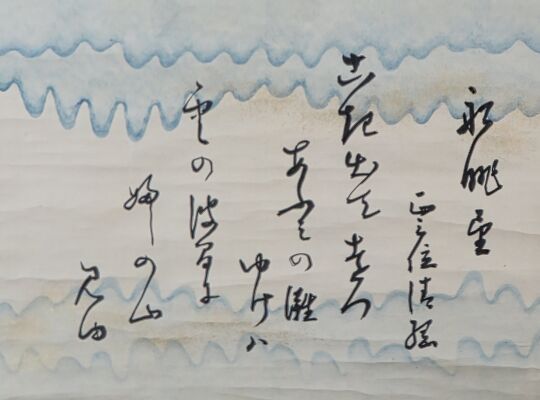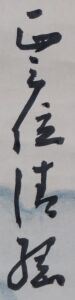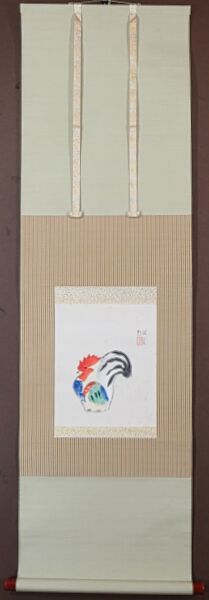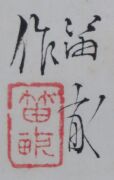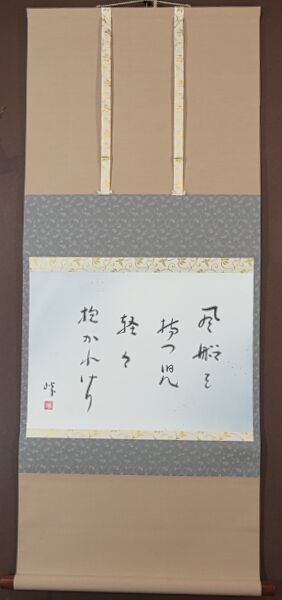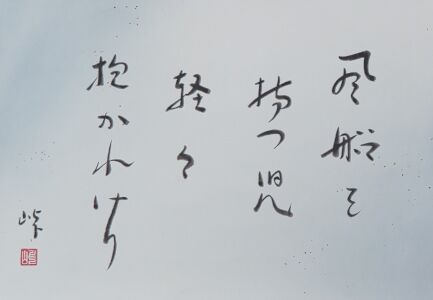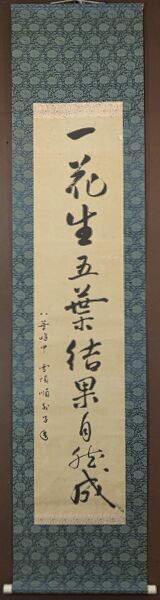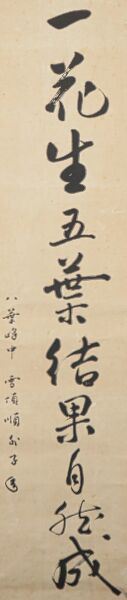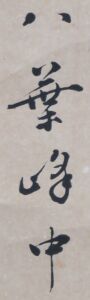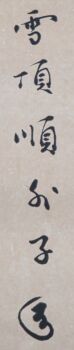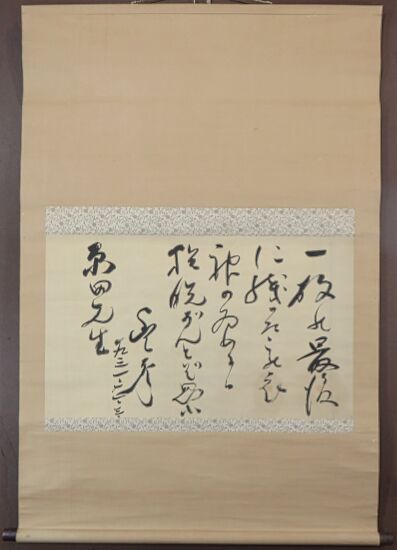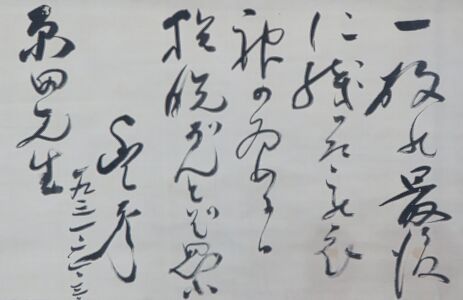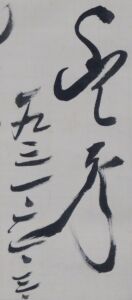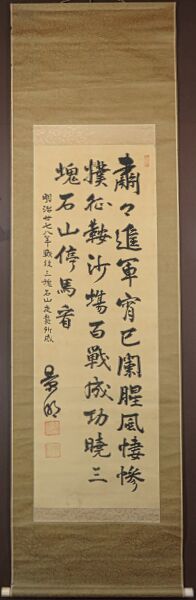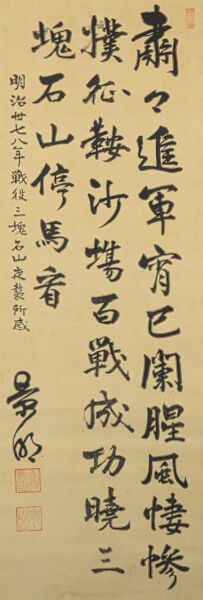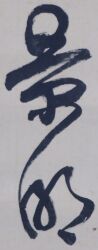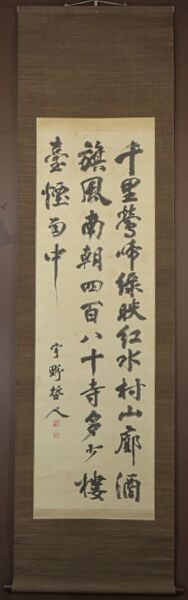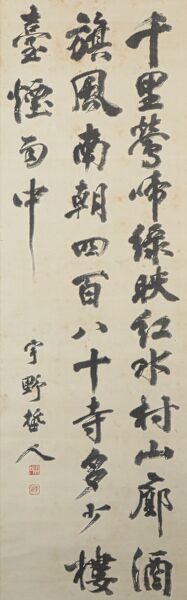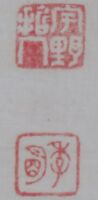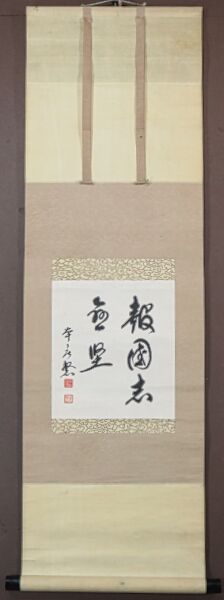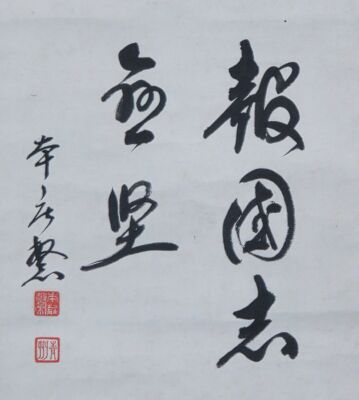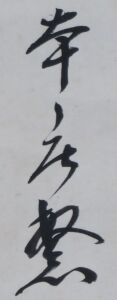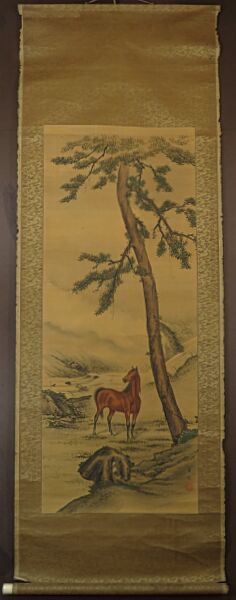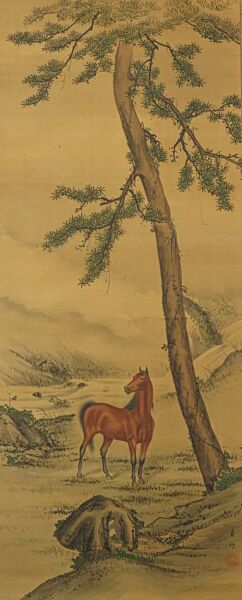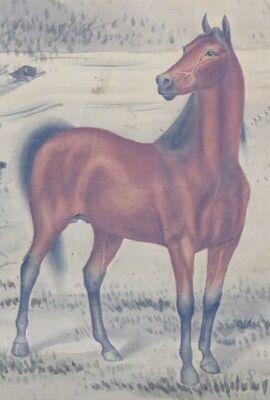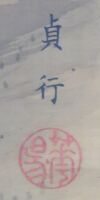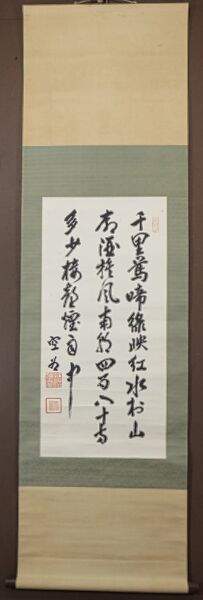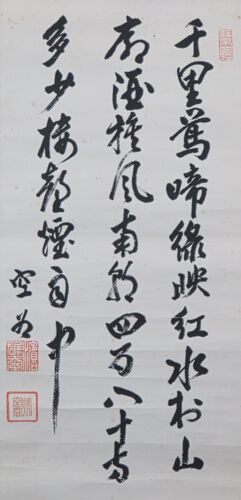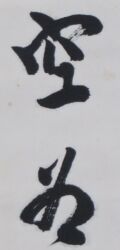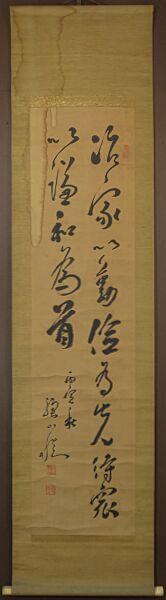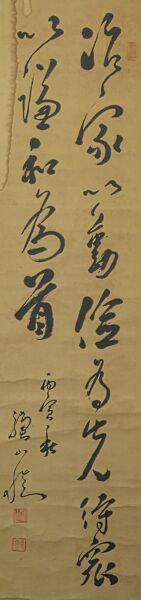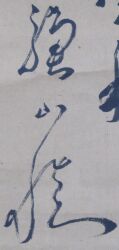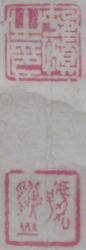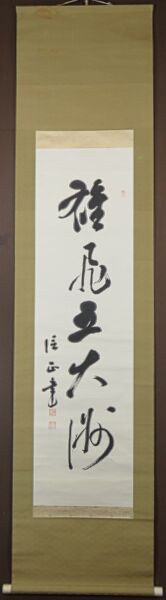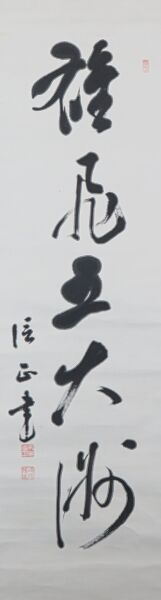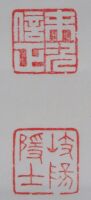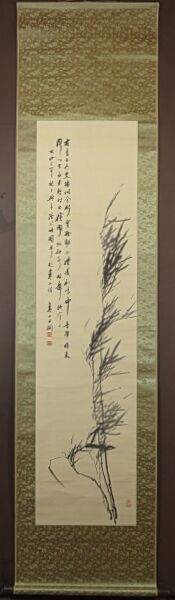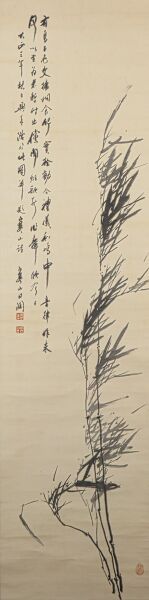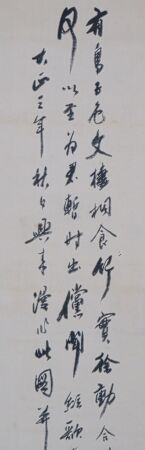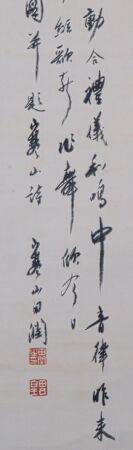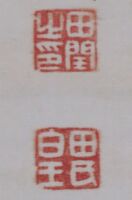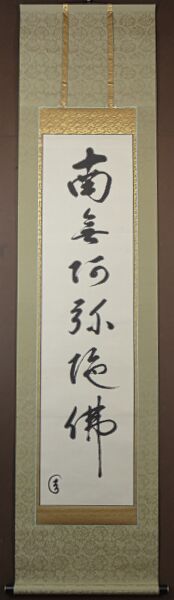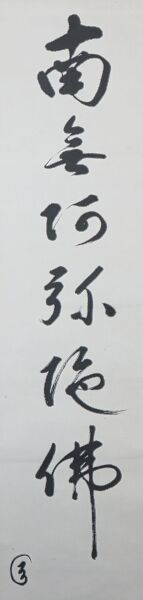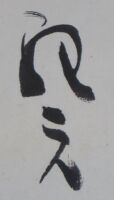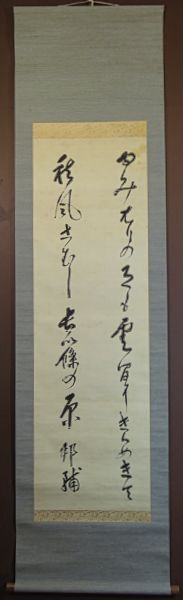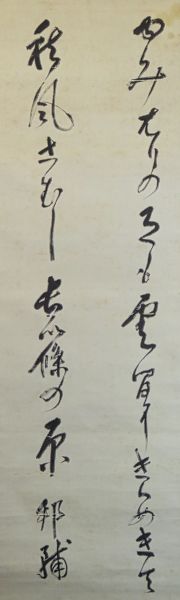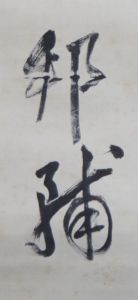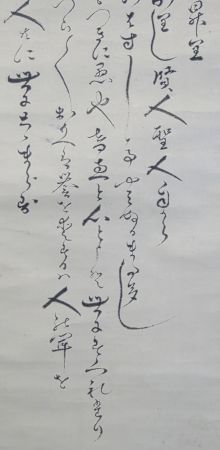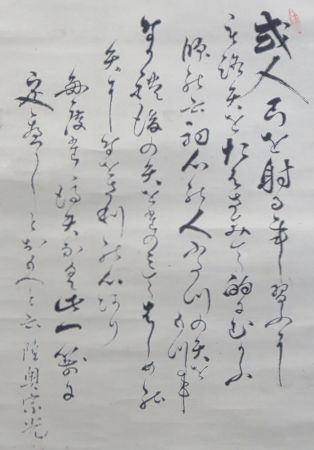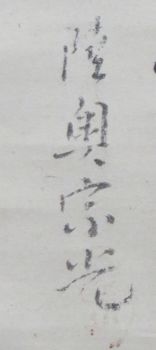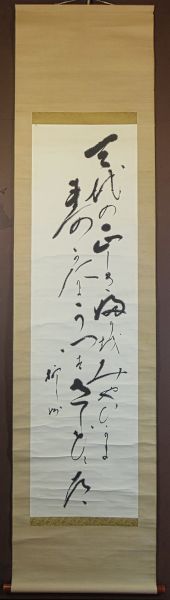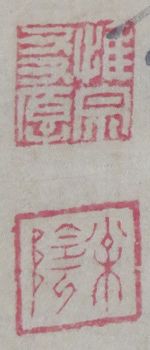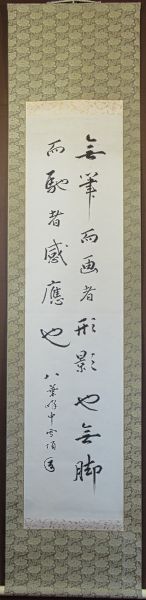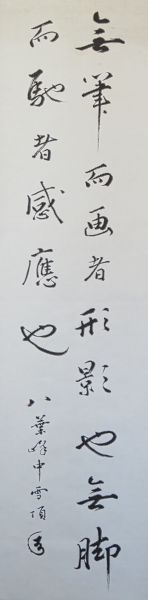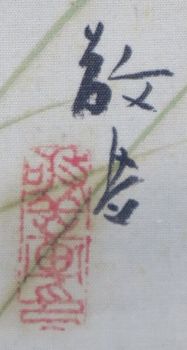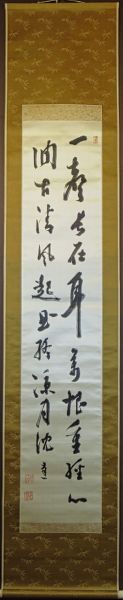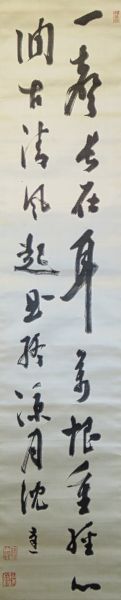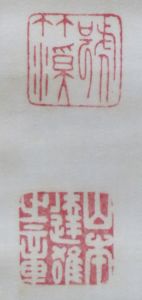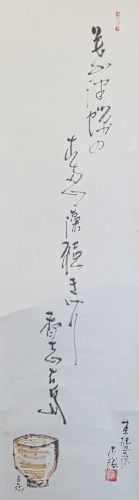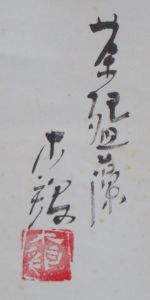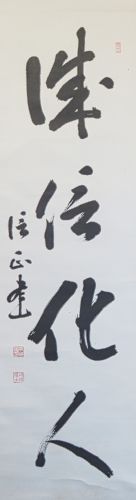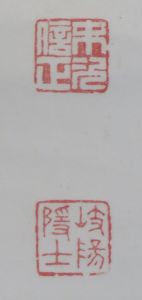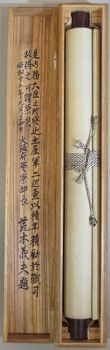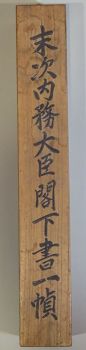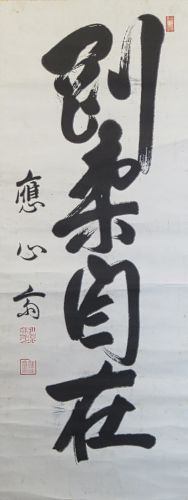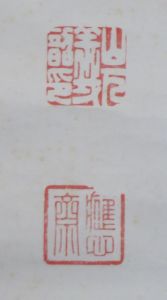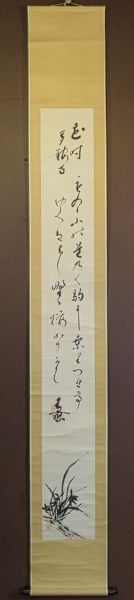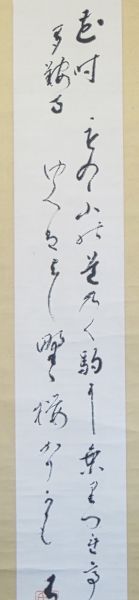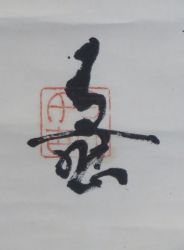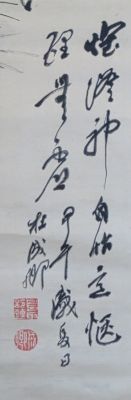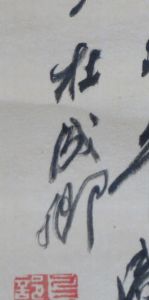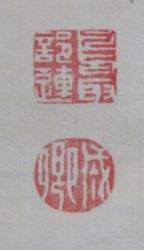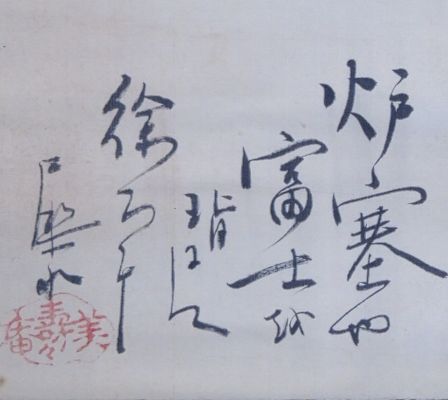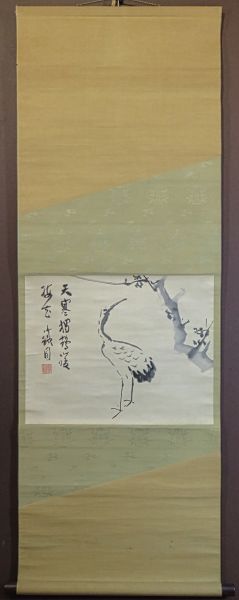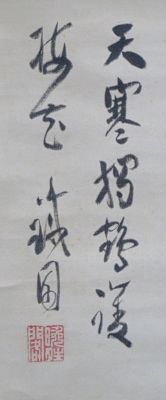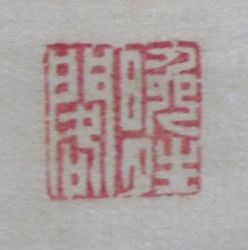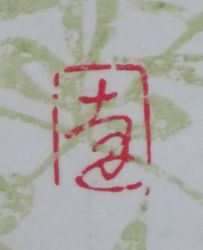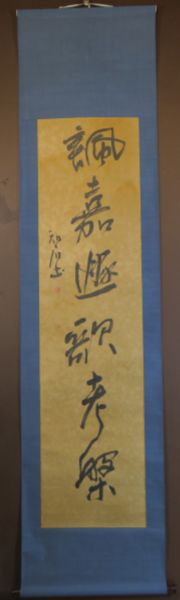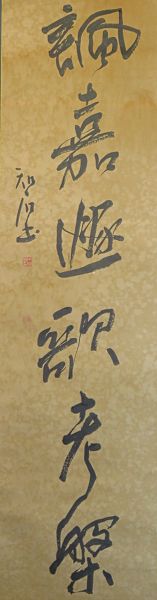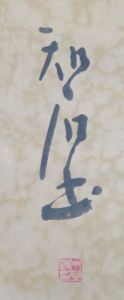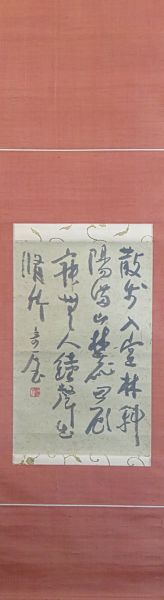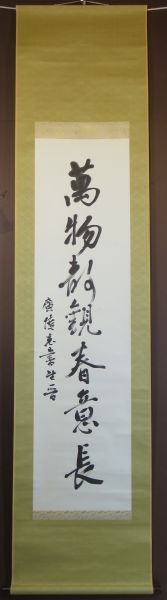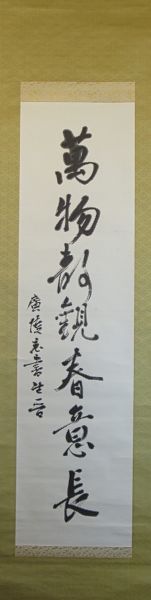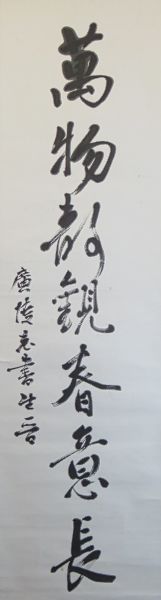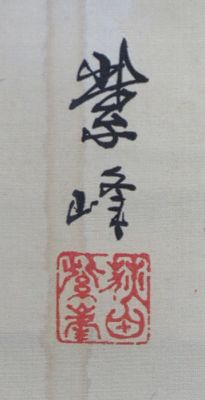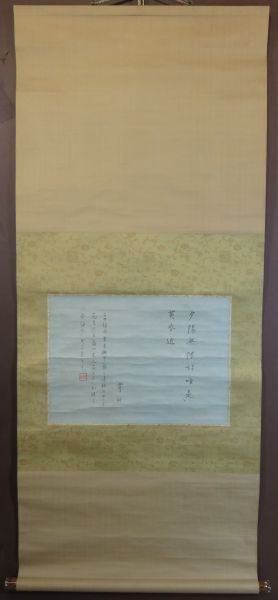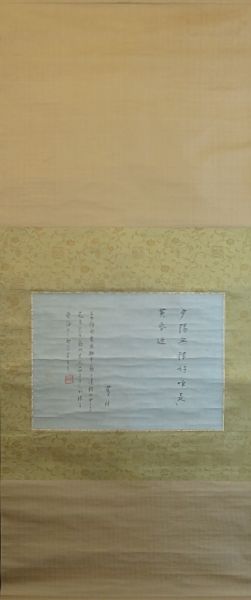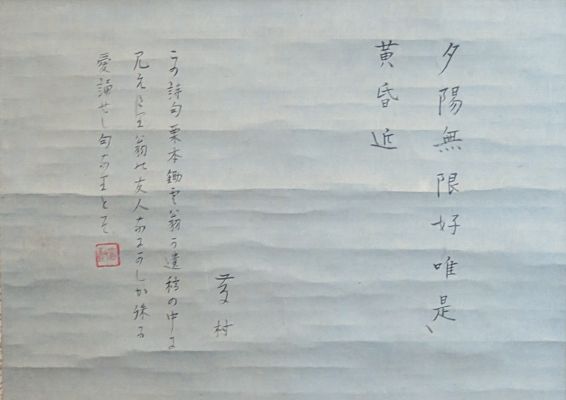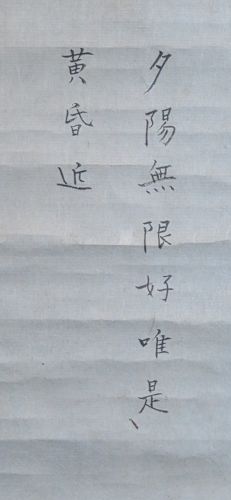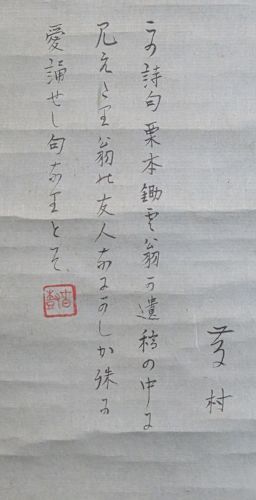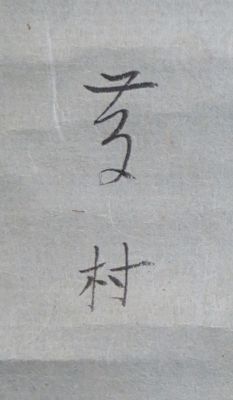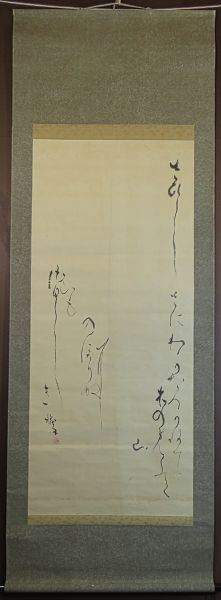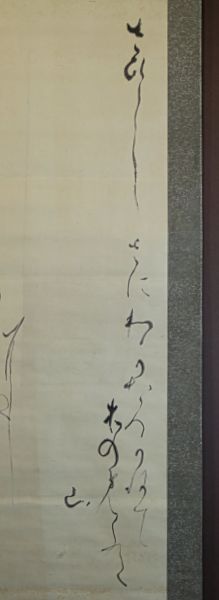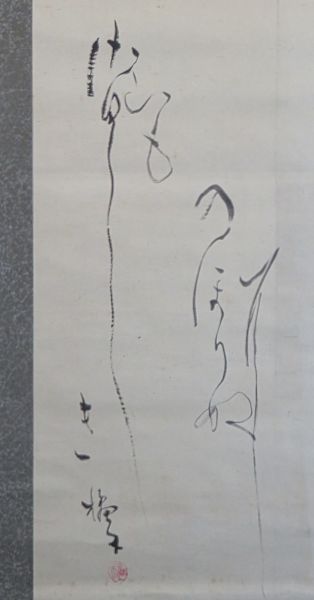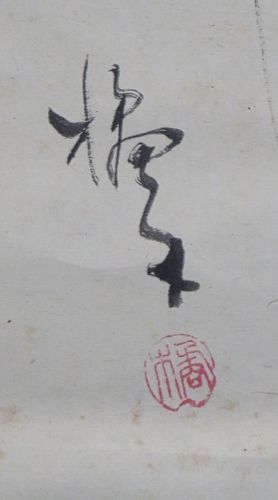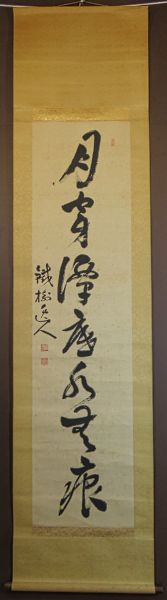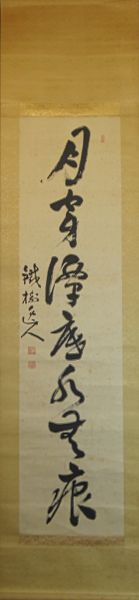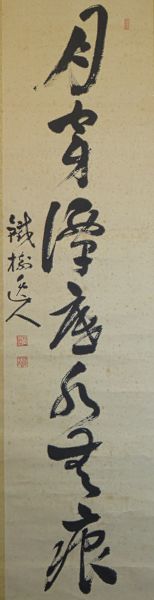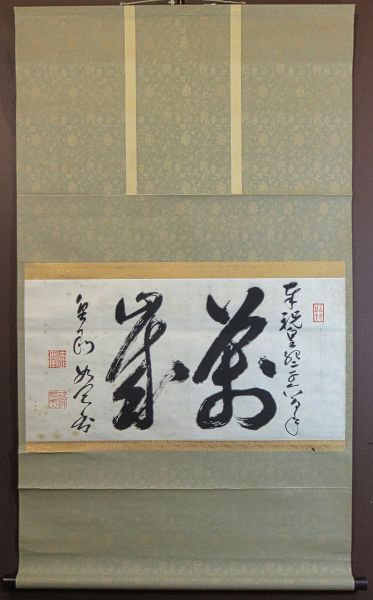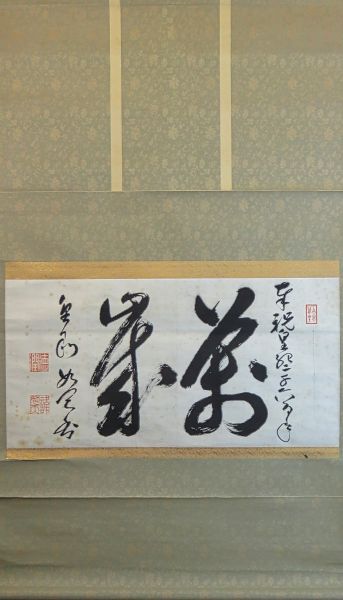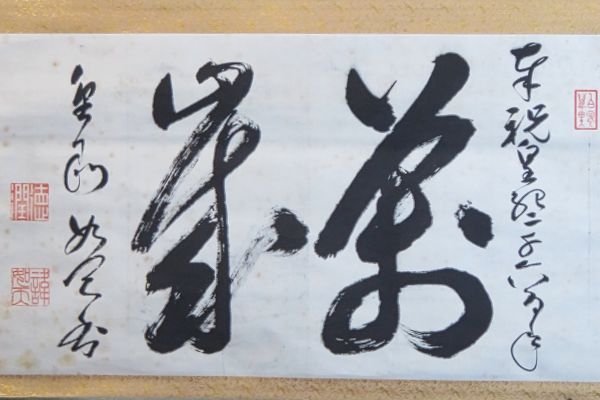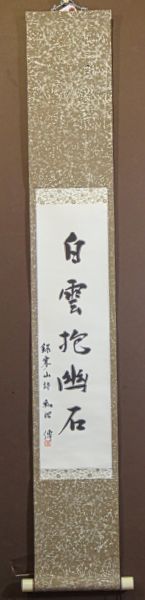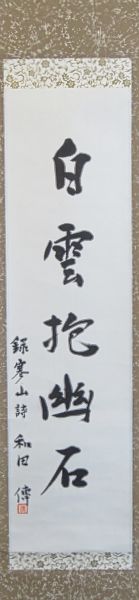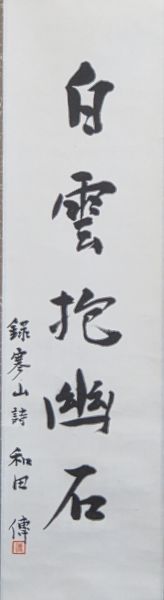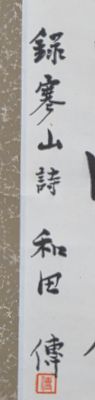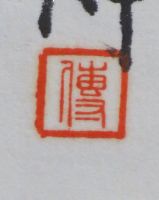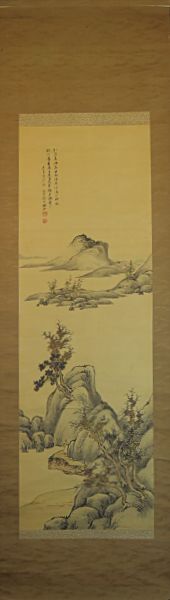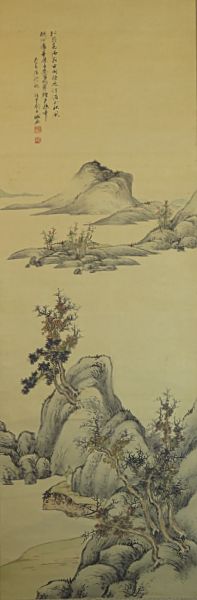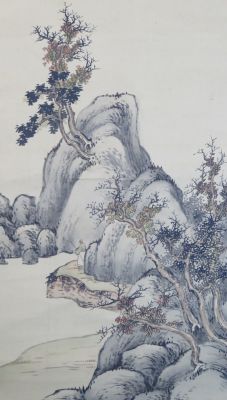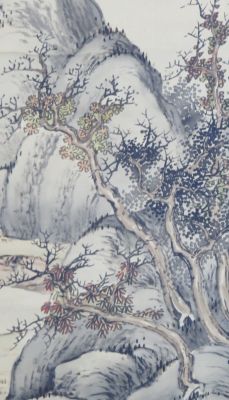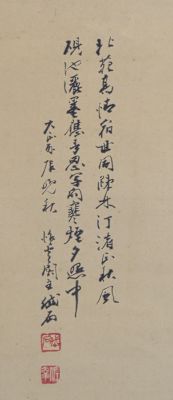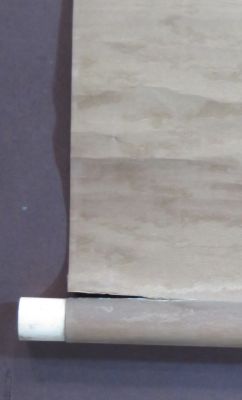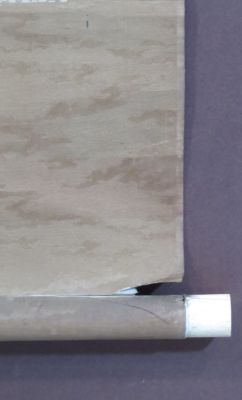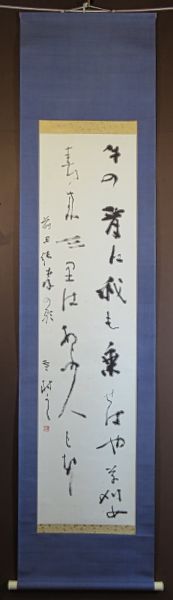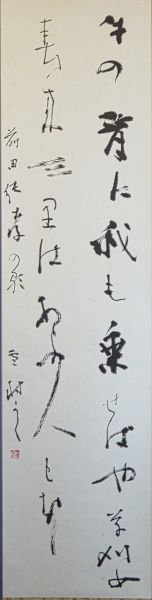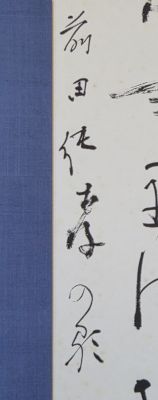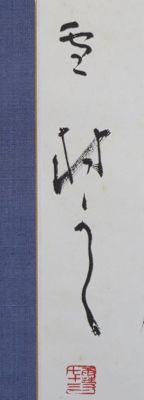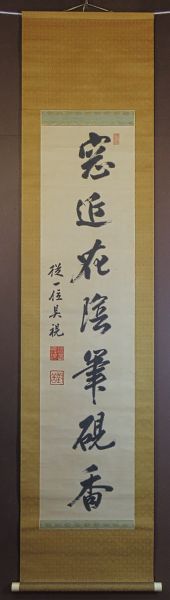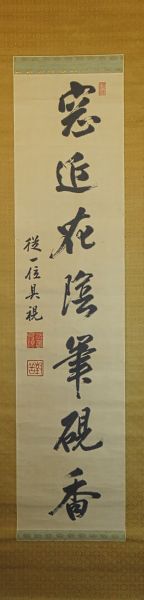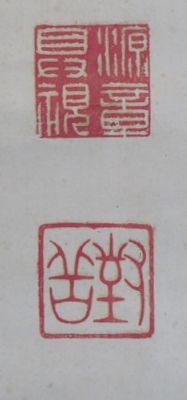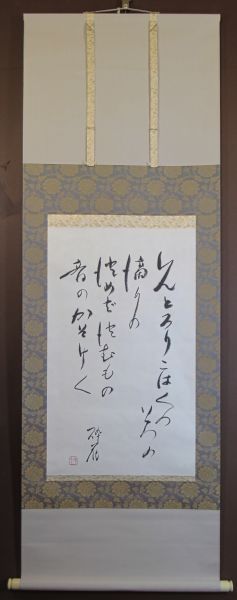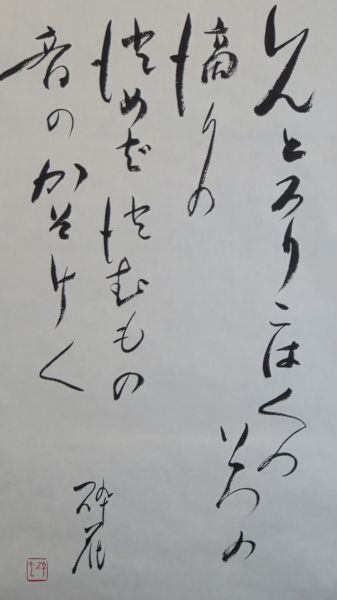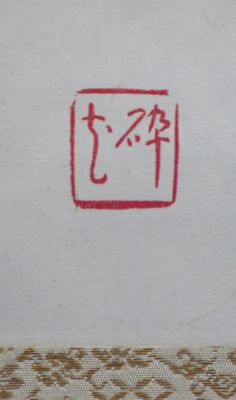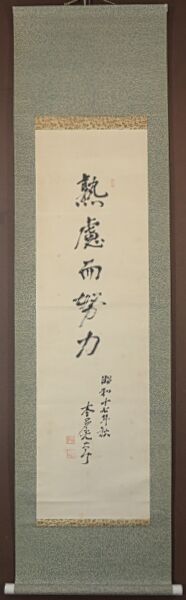
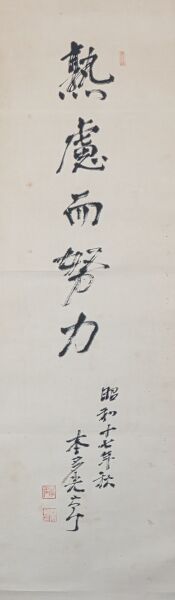
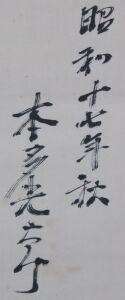
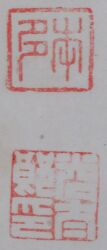
作家名 本多光太郎
作品名 一行書 「熟慮而努力」
略歴 本多光太郎(ほんだ こうたろう) 明治3年(1870)~昭和29年(1954)
金属物理学者、理学博士。愛知の生まれ。長岡半太郎とともに銅、ニッケル、コバルトなど強磁性
体の磁歪の研究に尽力した。ドイツ、イギリスの留学では物理冶金を修め、元素の磁気係数と温度
変化を研究した。また、強力磁石鋼(KS鋼)を発明するなど物理冶金学の確立などその功績は大きい。
東北帝大理科大学教授、理化学研究所主任研究員、日本金属学会会長、東京理科大学学長などを歴
任した。十大発明功労者の一人に選ばれ、英国鉄鋼協会ベッセマー賞、文化勲章を授与された。
価格 35,000円
詳細 紙本揉紙表具、軸先陶器
総丈 タテ169.5㎝ ヨコ44.5㎝
本紙 タテ112㎝ ヨコ32㎝
状態 本紙少シミ、オレアリ。